| 思いは人それぞれで、いろいろな思いが考えられますが、いくつか紹介しましょう。 |
○子どもの思い
・めずらしいもの、見たことのないものを見ると、すぐ驚きを口に出してしまう。
・悪気はない。
○障害のある人の思い
・一瞬、いやな思いをするが、子どもの発言なのであまり気にしない。
・母親のフォローに期待する。
|
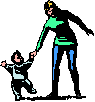 |
○母親の態度
・「そんなこと言っちゃダメ」と、たしなめる。
目をそらしていては、かえって子どもに自分と違う人に対して恐怖感を植え付けてしまうことにもなりかねなく、解決にはならない。
・「悪いことをすると、あーなるのよ」と、言う。
これは、社会の障害のある人に対する偏見以外の何ものでもなく、子どもに差別心を生み出しかねない。
・「片腕がなくて、可哀そうね」と、言う。
「かわいそう」という言葉、一見相手を思いやっているようだが、健康な身体の人が普通で、障害をもっている人は普通ではないという無意識の差別はないだろうか。このような同情的な説明は、場合により障害のある人を傷つけたり、かえって子どもに差別心を生み出しかねない。
・「あの人は、事故か病気で片腕がなく不便だけれど、手がなくても何でも出来るように練習しているのよ。世に中には足がない人や目の見えない人、耳が聞こえない人はたくさんいるのよ。」など、親として障害のある人に対して目をそらさないで、きっちり子どもに説明してあげることが必要で、健常者も障害者も一緒ということを教える。
世の中には、障害者に対し偏見を持っている人も実際いるのが現状です。間違った偏見を払拭し、その場、その場で子どもに教えていくことが大切です。 |
【筆者の思い】
1年程前にこんな体験をしました。朝の通勤電車に小学校高学年か中学生くらいの女の子とお母さんが乗車してきました。しばらくして女の子が急に奇声を発しました。突然の出来事だったので周りの乗客は皆ビックリしましたが、女の子のお母さんは何も言わずに女の子の髪を優しく何度もなでていました。女の子は安心したのか、じきにおとなしくなりました。その光景を目にして、「女の子が奇声をあげたのには理由があったこと、お母さんにはその理由がわかっていたこと」こんな当たり前のことがわかった気がしました。
障害者は「特別な人」ではないという意識を持つことはもちろん大切なことですが、それだけではなく、障害の種類もさまざまであること、それらの障害についてきちんと知ることも大事なことなのだと実感しました。
|

